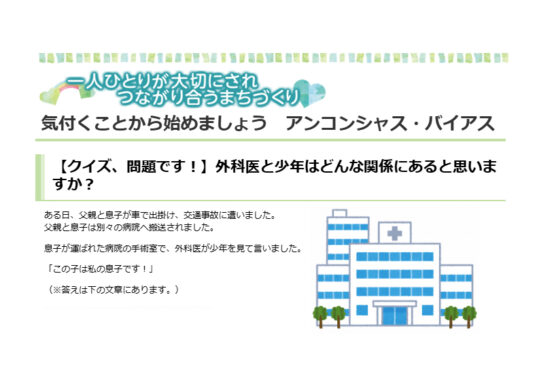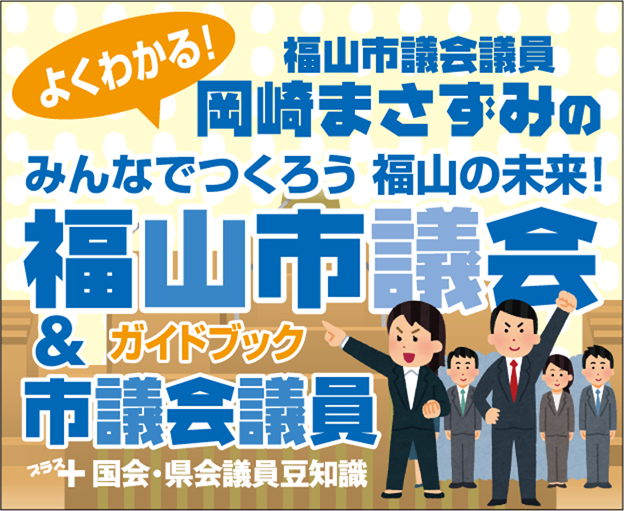【毎日新聞】
2023/4/22
木々が生い茂り、小川が流れる沖縄県・渡嘉敷島の山中に78年前、手投げ弾の爆発音や人々の悲鳴がこだまし、次々と住民が倒れていった。手投げ弾が不発だった家族は、首を絞められたり農具で殴られたりして殺され、残った人も最後は首をつるなどして自ら命を絶った。
1945年3月、島に上陸した米軍が迫る中、当時10歳の小嶺達雄さん(88)は、母や姉、兄の子らと輪になって座っていた。その一人一人の頭を、木の棒を手にした父が後ろから思い切り殴っていく。母は一撃で死ねず、血だらけで起き上がったところをまた殴られとどめを刺された。そんな光景を見ながらも「死ぬと決めていたから、怖くなかった」。父の気配を背後に感じ、次に気がついたときは米軍の収容所だった。
「生きて敵の捕虜になるのは恥」「捕虜になれば男は戦車でひき殺され、女は辱めを受けて殺される」。太平洋戦争末期、沖縄の住民たちに植え付けられていた旧日本軍の教えは、各地で起こったいわゆる「集団自決」の引き金となった。
沖縄本島の西約40キロに位置する慶良間(けらま)諸島では、米軍が上陸した3月26日以降、集団自決が相次いだ。座間味島で177人、慶留間(げるま)島で53人、渡嘉敷島では300人以上が亡くなったとされる。
犠牲者の多くは子どもたちだった。逃げようとする子を追いかける親の姿もあったという。小嶺さんは頭に大けがをしながら米軍に救助され奇跡的に一命を取り留めたが、兄の子ども4人のうち助かったのは1人だけだった。家族に手をかけた父は、木に首をつって死んでいた。
親のいない戦後の生活は「惨めだった」と振り返る。南洋の戦場から帰った兄たちの家を転々としたが、年の離れた彼らには家族があり、長くとどまることはできなかった。野宿をし、畑から農作物を盗んで飢えをしのいだこともある。
簡単な治療しか受けられなかった頭の傷は膿(う)んでウジがわき、汚れた布を集めて包帯代わりにした。頭をからかう同級生もおり、人前ではできるだけ帽子をかぶるようになった。その習慣は80年近く続いている。
「酒を飲むと思い出して涙が出る」。朝起きると枕に血がにじんでいることが今もあり、細かく砕けた骨は頭部に残ったままだ。「思い出したくない。でも、あのときのことは忘れず伝えていかねばならない」。集団自決の生存者が年々少なくなる中、そう強く思う。【喜屋武真之介】