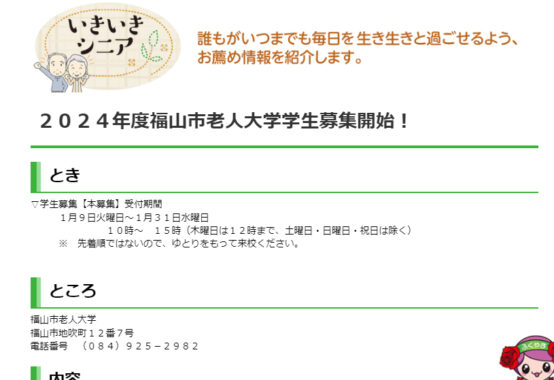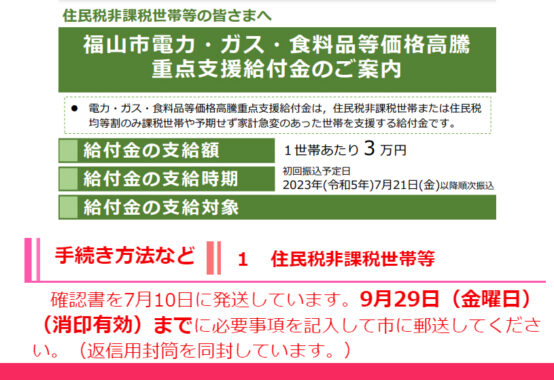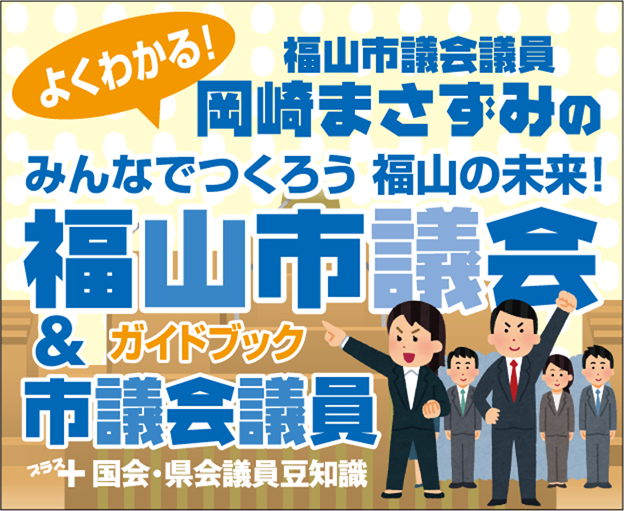【withnews】
2024.2.29
誰もが手話で「ありがとう」と伝えられる社会をつくりたい
聴覚障害者スポーツの国際大会「デフリンピック」が2025年に東京で開かれます。世界各国からやってくる3000人を超える聴覚に障害のあるアスリートを出迎える玄関口となる羽田国際空港では、いま多様なコミュニケーション方法で「おもてなし」する準備が始まっています。ユニバーサルデザインアドバイザーとして活動する聞こえない松森果林さんと、手話通訳士の聞こえる飯塚佳代さんのコンビが取り組む、手話をはじめとした対話スキルを学ぶ活動や、デフリンピックを契機に広がって欲しい価値について伺いました。
プロフィル
松森果林(まつもり かりん)さん
1975年、東京生まれ。10代で聴力を失った中途失聴者。聞こえる世界と聞こえない世界をつなぐユニバーサルデザインアドバイザーとして、企業、学校、一般向けに講演や手話セミナー、コミュニケーション研修を手がける一方、音のない空間で「対話」を体験するエンターテインメント「ダイアログ・イン・サイレンス」の日本初開催を企画監修し、現在もアテンドとして活躍。一般財団法人日本財団電話リレーサービス理事なども務める。
飯塚佳代(いいづか かよ)さん
1970年、東京生まれ。手話通訳士。20代半ばから手話を学び手話通訳士資格を取得し、2000年から通訳活動を開始。派遣通訳業務のほか、大学・専門学校での手話指導、松森さんとのコンビで、接客手話やダイバーシティー、ユニバーサルデザインにかかわる研修講師などを担当する。「ダイアログ・イン・サイレンス」では対話をつなぐ「サイレンス・インタープリター」として活躍。NPO法人ユニバーサルイベント協会理事を務める。
松森さんと飯塚さんが羽田空港で手話研修やセミナーを手がけるようになったのは2017年からです。羽田空港国際線ターミナル(第3ターミナル)の設計段階から松森さんがユニバーサルデザイン検討委員会に参加していた縁もあり、空港を運営する日本空港ビルデングの要請を受けて、同社の社員や関連会社の従業員ら空港で働く人たち向けに研修を開いてきました。これまでに約140回、延べ1500人が参加しています。

「手話で対応ができることを示すバッジをつけているスタッフも増え、『筆談用具を用意しています』といった表示が目立つところに置かれるようになりました。聴覚障害がある友人からも、『空港に手話ができる人がいてうれしかった』という声を聞きます。空港内の店舗で働く人たちが接客技術を競うコンテストでは、日本語、英語、中国語に加えて、2017年からは手話部門もできたんですよ」と松森さんは手応えを語ります。

いま、力を入れているのは2025年に開催されるデフリンピックへ向けての取り組みです。世界約80カ国・地域からやってくる3000人のデフアスリートたちにどう対応するかが大きな課題です。基本的な手話はもちろんのこと、顔の表情やボディーランゲージ、筆談、音声認識アプリなど、あらゆるツールを使って、多様なコミュニケーション方法を楽しむ実践的な研修を継続しています。
「日本人は表情や感情表現が苦手だとされていますが、一概にはいえないと思っています。例えば、能面の表情が光のあたり方で怒りや笑いなどに変わることを感じ取れる繊細な感性も持っていますよね。だからこそ、ほんとうは日本人も豊かな表情や身体表現でコミュニケーションを楽しめると思うのです」

その可能性を実感したのは、言葉を使わずに「対話」を楽しむドイツ生まれのエンターテインメント「ダイアログ・イン・サイレンス」の日本開催の企画監修に携わった経験からでした。参加者は音を遮断するヘッドセットをつけて、アテンド役の聴覚障害者の案内で、音や声に頼らないコミュニケーションを体験します。
「最初は、みな下を向いて目も合わせられない状態から、目や眉など顔のパーツひとつひとつの動かした方を一緒に覚えていくうちに、どんどん表情が豊かになっていきます。初対面同士でもアイコンタクトをとりながら、言葉の壁を超えた意思疎通ができるようになる、その変化は見ていて感動的なほど」と松森さん。こうした実体験を研修のヒントにしています。

言葉だけに頼らないコミュニケーションの出発点は「まず、相手の目を見ること」だと松森さんは言います。「ろう者の文化では、目を合わせないことは、『私と話す意思がない』と判断されてしまいます。手話を知らなくても、目と目を合わせ、ちょっとした身ぶりや表情で『こちらへどうぞ』と伝えることができます。コミュニケーションは意外にシンプルな部分もあることを、もっと知って欲しいと思います」
もう一つ、この研修でユニークな点は「聞こえない講師と聞こえる講師が対等な立場で、お互い自分の思ったことを言い合って進めていく。この自然な関係が心地いいんです」と手話通訳士の飯塚さんは言います。
二人はもともと、松森さんが暮らす地域の派遣通訳者と依頼者として出会いました。そこから意気投合し、6年前から専属通訳者の一人として、会議や講演会からパーティーなどの懇親会の場まで共に活動するようになりました。
「私の場合、手話通訳者は仕事だけでなくプライベートも含めて一緒に楽しめる方と組みたいと思っています。現状では個人が専属の形で契約するしかありませんが、もう少し柔軟な仕組みや通訳者の働き方があってもいいと思います」と松森さんは指摘します。手話通訳という仕事は、本来「黒衣(くろこ)」役で、聴者が話した内容を手話で正確に伝え、聞こえない人が伝えた手話を正しく日本語で伝えるのが使命です。自分の気持ちを伝えたり、個人の個性を出したりすることは求められません。

「もちろん、通訳者としての原点は大事にしなければいけませんが、もう少し幅を広げた“通訳”の関わり方があってもいいのではないかと感じています」と飯塚さんも話します。
「複数人での会話で手話通訳に入る時によく感じるのですが、聞こえない人は通訳を介して情報を得ているので、聞こえる人と時差が生じ、意見などを言うタイミングがつかめないことがあります。そのような時に通訳者が音声で「〇〇さん(聞こえない人の名前)はどうですか?」と声をかけて、会話に巻き込むことができればコミュニケーションを深めることができる。通訳本来の役割からははみ出してしまうのかも知れませんが、可能性も感じます。果林さんとの仕事は、そうした自分らしさを発揮したチャレンジができるので、やりがいを感じています」
そんな飯塚さんと手話との出会いは、自治体が主催する「手話講座」でした。1990年代半ば、結婚を機に退職し専業主婦をしていた時、たまたま広報紙に載っていた案内に目がとまったそうです。「大人になってもゼロから勉強できることがあるって、うれしいじゃないですか。学生の時には気づかないですが」。講座や各地の手話サークルに参加し、手話の面白さに夢中になりましたが、手話通訳士を目指したわけではありませんでした。「ろう者の知り合いが増え、新しい世界に触れることが楽しかったんですね」。資格は周囲に勧められて取得しました。
今は大学や専門学校で手話講座を担当したり、企業で働く聴覚障害者向けの研修やダイバーシティーの研修を企画したりする仕事もしています。「日本人って、相手に対して失礼だという思いが先に立って、分からないときに分からない顔をするのが苦手ですよね。学生たちには分からないなら困った顔をする、困ったジェスチャーで伝えることが大事だよ、と教えています。また、手話は日本語のような回りくどい表現をしないため、ろう者が日本語を使う際にストレートな言い方になりがちで、失礼な人に思われるなど誤解を招くことがあります。お互いの文化や習慣を理解する橋渡し役になれればとも思います」

飯塚さんは手話を学ぶ意味や喜びについて「新しい言葉を知ることで、自分のコミュニケーションの幅や世界の見方が少し広がり、それを生かして、自分や世界を少しずつ変えていくことではないか」と話します。そして、こんなエピソードを紹介してくれました。
接客手話の授業を受けた学生のアルバイト先に、聞こえないお客さんが来た時のこと。同僚たちがおたおたする中、学生は勇気を出して応対したそうです。その時、たまたま授業で覚えた指文字が通じたことが自信になりました。今では聞こえない人が来店すれば、自分の役割だと思って接客する自覚や責任感を持つまでに変わっていったそうです。
「こうしたコミュニケーションのチャレンジを楽しめる人が、社会全体でもっともっと増えていけば、誰もが生きやすい社会になっていくのではないでしょうか」と松森さん。そのためにも、まずは東京2025デフリンピックが、聞こえない人の存在を知り、つながっていくチャンスになって欲しいと松森さんも飯塚さんも願い、大会本番に向けて、空港という出会いの舞台で、様々なイベントを展開したいと考えています。
「英語の“サンキュー”という言葉は誰でも知っていて、みんな自然に口に出せますよね。同じように、誰もが手話で“ありがとう”を伝えられる世界になったら素敵だと思いませんか?」