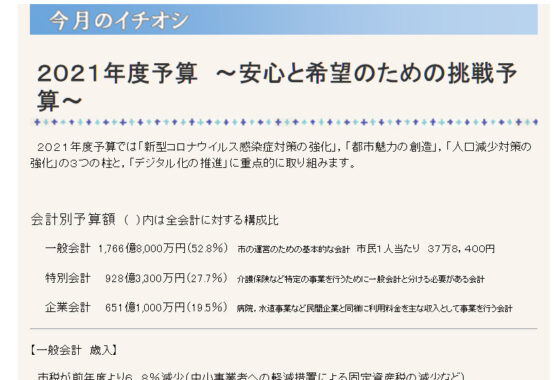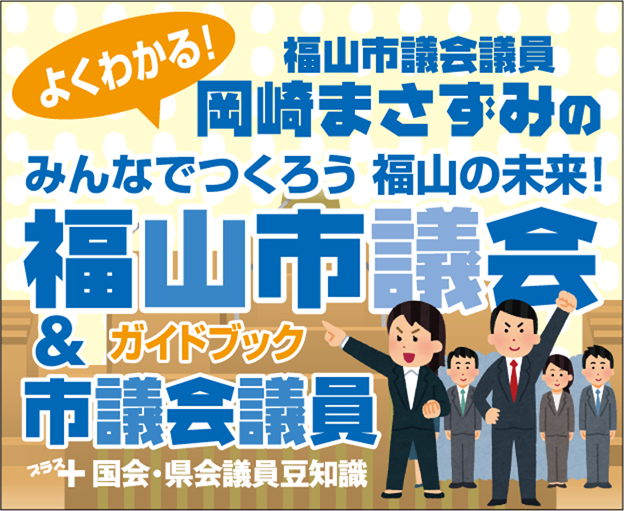【産経新聞】
2022/11/23
強い毒性を持つ高病原性鳥インフルエンザが猛威を振るっている。22日現在、1道9県の養鶏場で14例が確認され、ニワトリの殺処分数は275万羽を超えた。過去最多だった2シーズン前を上回るペースで感染が広がり、国内では初めて3季連続の感染が確認された。欧州で過去最大の発生が続くなど世界的流行に起因するとみられるが、日本でも今後毎シーズン発生する懸念が高まる。
環境省によると、今季の1例目は9月25日、神奈川県に飛来した野鳥から採取し、確認された。例年であれば、海外から多くの渡り鳥が飛来する10月下旬以降に最初の感染がみられるが、今季は1カ月以上も早かった。以降、北海道や岡山、香川、鹿児島県など1道9県の養鶏場に飛び火し、自治体では家禽(かきん)の殺処分や消石灰の配布などの防疫対策に追われている。同省の担当者は「もはや全国どこでも発生のリスクがある」と話す。
今季のこれまでに発生した家禽の鳥インフルエンザは、いずれも致死率の高い「H5型」が検出された。生きたニワトリがウイルスを増殖し拡散させる恐れがあるため、養鶏場からの移動は制限され、家畜伝染病予防法に基づく殺処分の対象となる。
国内では平成15年度の冬シーズンに79年ぶりとなる高病原性鳥インフルエンザが発生、この年は約27万羽が殺処分された。その後は数年に1度のペースで起こっていたが、令和2年度には過去最大の約987万羽、翌年度は約189万羽を殺処分するなど、近年は発生周期が短くなり、感染規模も拡大の一途をたどっている。
感染経路は、ウイルスに感染した渡り鳥を通じて海外から日本に持ち込まれると推定されるが、飛来シーズンである10月下旬から3月下旬にかけて頻繁に発生する。ただ、欧州を中心に2季連続で世界的な感染拡大が続いており、韓国でも感染に歯止めがかからない状況が続く。
鳥インフルエンザに詳しい農研機構動物衛生研究部門の内田裕子グループ長は「今シーズン、日本で検出されたウイルスの型は世界的に流行しているものと同じ。夏の間シベリアの営巣地に集まった渡り鳥の間でウイルスが受け継がれている」と指摘。「2014(平成26)年以降はウイルスに含まれる遺伝子の性質が変わり、これまで以上に野鳥を媒介して感染が広がりやすくなっているのが特徴だ」と警鐘を鳴らす。
一方、感染の急拡大は、消費者にも影響を与える。ウイルスは熱や酸に弱く、鳥からヒトには感染しにくい。国の食品安全委員会も「鶏肉や卵は食べても安全」としているが、仮に茨城や宮崎、鹿児島県など国内有数の産地でさらに感染が長引けば、鶏肉や鶏卵の需給にも影響が避けられない。ただ、これまでの殺処分数は、国内で飼育する採卵鶏とブロイラーの総数の1%未満にとどまり、農林水産省は「現時点では需給への影響は考えにくい」としている。(白岩賢太)