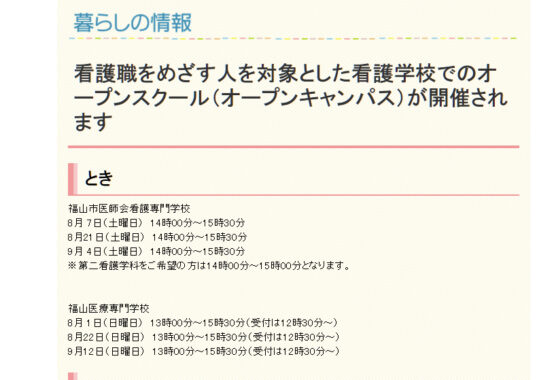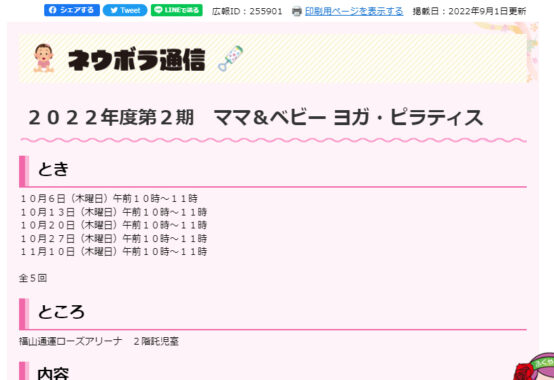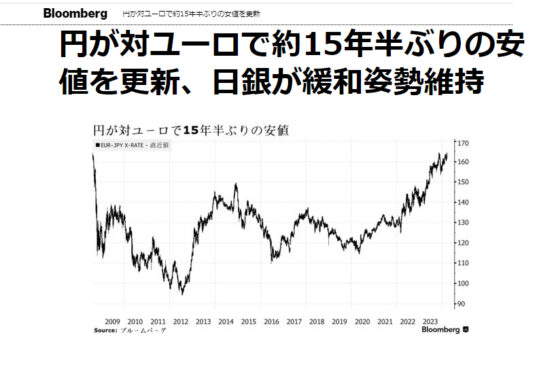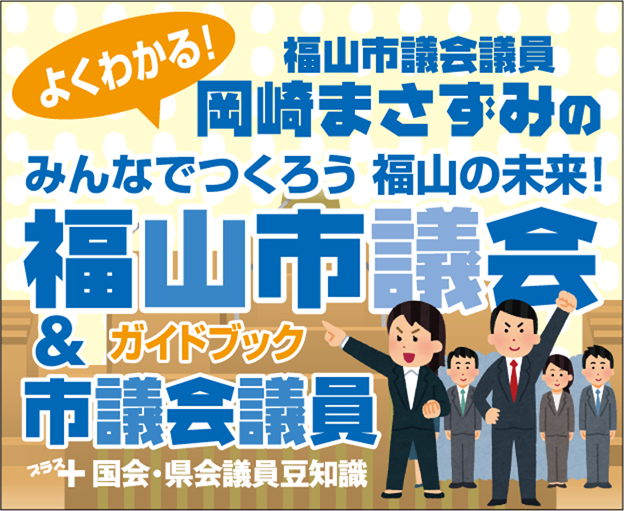【東洋経済】
2022/12/02
あと、「システム」という響きが纏っている、脆弱なニュアンスも、多少引っかかる。「システム」って、なんだか変化に弱い印象があるのだ。
たとえ「自分だけの経済システム」を獲得したとしても、もし、万が一、なにかのきっかけで私がついタイムカード打刻機に水を注ぐようなことをしたら、一気にそのシステムは「プシュン」と音を立てて消えてしまうんじゃないか。そんな印象から、どうにも「自分だけの経済システム」という言説には眉に唾をうっすらとつけながら聞いてしまう自分がいる。
だから、私にできることは、こうして闇雲に石を売ることだけだった。資本主義という大きな「経済システム」の枠外で、需要と供給の大原則をおもいっきり無視して、誰も求めていない石を売る。もしかしたら、それがなんかの拍子に、世に名高い「自分だけの経済システム」に化けるかもしれないじゃないか。いや、「システム」を超える、もっと有機的な何かに、化けるかもしれないじゃないか。その瞬間、私はお金に「勝つ」ことができるかもしれないじゃないか。勘だけど。
しかるに問題は、そもそも今日、石が売れなかったことである。結局、私は引き続きお金に負けながら、黙々と会場の公園で片付けに従事していた。
その『手づくり市』は、2日間連続開催のイベントだった。だから、私は明日もここで出店をする予定だ。
ああ、このままでは、きっと明日も売れない。深いため息を、ひとつ吐く。
よく考えたら、「石ひとつ100円」の紙が貼ってあるだけの不気味なカウンターに、誰が寄りつくというのか。
私に足りていないのは、工夫なのだろう。だが、どのように工夫すれば石が売れるのか、それが皆目見当もつかなかった。
結局、最後は液体が勝つんです
「おつかれさまです、石は売れましたか?」
片付けをしている私に、そう声をかけてくる人が現れた。私の隣で、自家製のシロップから作ったジュースやアルコールを販売していた女性である。彼女の屋台はお客さんの波が途切れず、常ににぎわっている印象だった。日中、暇を持て余していた私はそれをずっと羨ましく眺めていた。
「いや、全然売れませんでした……」
「そうですか……。いや、石を売っているお店なんて初めて見たから、驚きましたよ」
そう言うと彼女は、売り物のジュースを一杯、「ねぎらいの代わりです」と私に恵んでくれた。ありがたくそれをいただき、喉を潤す。美味しい。
お礼に、石をひとつ、私からプレゼントした。彼女は笑って、それを受け取ってくれた。
飲み物をもらって、石でお礼を返す。私は初めて人間との触れ合いを持った子ダヌキなのか。