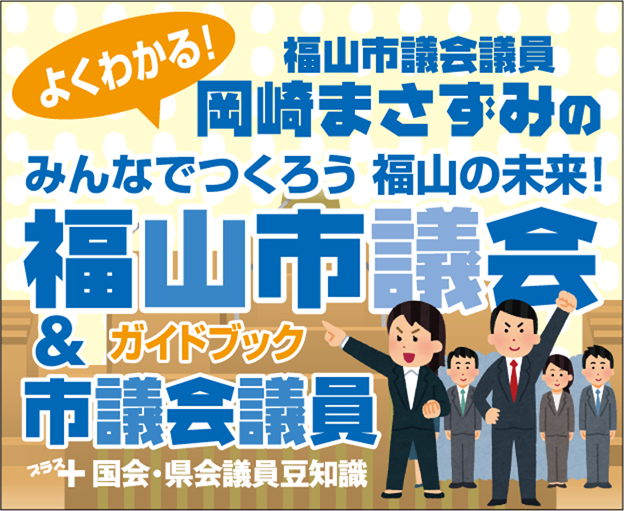【goetheweb.jp】
2022.10.24
2022年9月に81歳を迎え、今も休みなくトップを走り続ける建築家・安藤忠雄。GOETHEは創刊以来16年間、安藤さんを追い続けてきた。今回は大阪に足を運び、安藤さんの80代の仕事人の在り方をインタビュー。短期集中連載「安藤忠雄が走る理由」。その第1回となる今回は、ゲーテ2009年8月号より当時68歳の安藤忠雄特集を蔵出し。

今、この瞬間も世界中の現場で闘っている。
「独学で建築家になったという私の経歴を聞いて、華やかなサクセスストーリーを期待する人がいるが、それは全くの誤解である。閉鎖的、保守的な日本の社会の中で、何の後ろ盾もなく、独り建築家を目指したのだから、順風満帆に事が運ぶわけはない。とにかく最初から思うようにいかないことばかり、何か仕掛けても、たいていは失敗に終わった」
2008年秋に出版された自伝で、彼はそう述懐している。謙遜でも自嘲でもない。本心から、そう書いているのだと思う。
建築家、安藤忠雄。彼は閉塞した現代社会に巨大な風穴をあけた。日本を支配する学歴社会、縦割り社会に新風を吹き込んだだけではない。今日でも国際感覚の乏しい島国日本において、東京一極集中の偏った状況に抵抗し、閉塞感の元凶となっているあらゆる既成概念に常に挑戦し、突破しながら、世界的に認められた建築家となった。大阪に生まれ育ち、活動の拠点としながら、国内だけでなく、アジア、ヨーロッパ、アメリカの各地で活躍を続ける安藤は、日本社会の異端児といってもいい存在だ。
「中学2年生のとき、祖母と住んでいた長屋を、平屋から二階建てにしたんです。そのとき、近所の若い大工さんが一心不乱に働いていたんです。昼飯もろくに食べずにね。これは何かすごく面白い仕事なんじゃないかって思った。それがずっと心のどこかに残ってたんですね。でも、家庭の経済状況と、自分の学力を考えれば、大学には行けない。ならば自分で勉強すればいいと考えて、独学を始めたんです。世の中そんなに甘いはずはないんですが……」
建築家という職業を、最初から明確に意識したわけではない。木工所に鉄工所、鋳造所、ガラス工場……。彼の育った大阪の下町には、ものづくりの町工場がひしめいていた。工業高校の機械科を卒業したから、図面を描くことはできた。ものづくりの現場でアルバイトをしながら、見よう見まねで家具の設計をし、インテリア設計の仕事を請け負い……。何かに導かれるように、建築家という職業に引き寄せられていった。

今まで取材した中で最も細かく書き込まれたスケジュール帳。実はこの分刻みの予定を安藤はすべて記憶し、見なくても予定がわかる。
「10代の終わり頃、大阪の道頓堀の古本屋で、建築家ル・コルビュジエの作品集を見つけたんです。パラパラとめくって、これは絶対に買おうと思った。だけど、高すぎて手が届かない。どうしても欲しかったので、店に行くたびに、その本を一番下に押し込んで帰った。しかし、次に行くと、その本がまた一番上に戻されている(笑)。2ヵ月ほどそんなことを繰り返しながらお金を貯めて、ようやく買うことができた。
その中に、ロンシャンの礼拝堂の写真がありました。その礼拝堂の周りにたくさんの人が集まっている。建築はこんなに人を集められるんだということに感動しました。そのときですね、建築の公共性というのを意識したのは。建築って、建物をつくるだけじゃなくて、人々の生活や意識までも変えてしまえるものなんだと。それで、建築家になることを心に決めました」
建築の美しさや込められた思想だけではなく、生き方においても、コルビュジエは安藤の人生の師となった。彼は時計職人の学校を出ただけで専門教育を受けていない。近代建築の巨匠コルビュジエもまた、独学の建築家だったのだ。
「大学の建築科で使っている教科書すべてを、1年間で読破すると決めて、朝から夜中の3時過ぎまで、毎日本を読んでいた年もありました。子供の頃は毎日そこらで喧嘩ばかりしてた子が、家に籠もって大丈夫かと、近所の人が本気で心配していたほどです(笑)。
だけど、僕は子供の頃に、ちゃんと子供をしていたからこそ、1年間そんな生活をしても、平気でした。小学生の頃は、放課後は魚釣りに、トンボ捕り、野球をしたり、喧嘩をしたり。そこで自分の思うとおりにならないのが自然だということも学んだし、喧嘩しながら、人間同士のつきあい方も学んだ。判断力も、忍耐力も、みんなそこで身につけた。
たぶん放課後に学んだことが、今にいたるまで創造力の源になっているように思うのです。ところが、今の子供たちは放課後に自然と触れ合ったり仲間と遊ぶ時間もなく、勉強ばかりしているから、社会に出てからちょっとした理不尽なことに耐えられずに引き籠もってしまう。子供時代には真剣に子供することが大事なんです。その頃に培った、精神的体力と闘争心が、大人になってから、生きる力、考える力、創造力の源になるんです」

数え切れないほどのプロジェクトの細部まで記憶している。それは、安藤がひとつひとつの仕事に命がけだからだ。
無我夢中の時間の中にこそ、人生の充実がある
1964年に日本人の海外旅行が自由化されると、アルバイトで貯めた金を握りしめ、ヨーロッパやアメリカに出かけるようになった。ジェット機の旅ではない。貨物船や、鉄道を乗り継いでの旅だった。世界中の、古代から現代までのあらゆる建築を見て、脳裏に焼き付ける旅だった。「この旅で初めて、地平線と水平線を見ました。世界の大きさと深さを意識したのもこのときです」
そして1969年、28歳にして大阪の梅田に、小さな建築事務所を開設する。もちろん、事務所を開いたからといって、仕事の依頼が来るわけではなかった。建築コンペに参加するのがほぼ唯一の仕事という状態が、長く続いた。
「それでも、まれにチャンスをくれる人がいる。そこでまた失敗するわけですよ。失敗例は無数にある。30代の中頃までは、頼まれたのだから、『あとのことはご自由にどうぞ』と任されているというくらいにしか思っていなかった。実に勝手気ままな建築士だった」
建築家としての実質的なデビュー作となった〈住吉の長屋〉が完成したのは1976年、安藤は35歳になっていた。間口2間、奥行き7間の住宅だ。その住宅を、安藤は3等分して、真ん中の3分の1を中庭にしてしまった。1階の居間と食堂、2階の夫婦の寝室と子供部屋は、屋根のない中庭で隔てられ、雨の日は傘を差して移動しなければならないのだ。
「ある建築の賞の審査員として村野藤吾先生が見にいらっしゃったんですけど、『設計した人間よりも、この住宅に住んでいる人に賞を与えるべきだ』と言われました。こんな勇気ある住まいをつくらせて、不便を我慢して住んでいる施主さんが、偉いんだって。そのときはじめて、建築は施主との共同作業であり、周囲を意識しなければならないのだと悟りました。それからは、クライアントの話も聞くようになりました。30%くらいはね(笑)。でも、やっぱり本質は変わらないね。大人にならないからね。私はもう、大人になったら負けだと思ってますから」

言うまでもないが、これは安藤が自分の好き勝手に設計しているという話ではない。彼は圧倒的なくらい真剣に、依頼者の生活のことを考え抜いているのだ。それがしばしば理解されないのは、彼が依頼者自身よりも深く考えてしまうからだ。
便利に、快適に暮らせれば、それでいいのか。その場所で生活を営むために、本当に必要なものは何なのか。そこまで徹底的に考えて、彼は設計する。〈住吉の長屋〉で言えば、彼は「自然の一部としてある生活こそが住まいの本質なのだ」という答えを出した。周囲の自然から切り離された都会の住宅密集地の14坪という限られた空間だからこそ、厳しさも優しさも含めた自然の変化を最大限取り入れるために、無難な便利さを犠牲にしても、中庭が必要だと彼は考えた。それこそが、人がそこで生きるということなのだと。
文明の進歩が人間性を阻害しているということは、現代人なら誰もが気付いている。けれど、それならばその文明の受け皿である都市を、どう形作るべきか。どうすれば人間性を回復できるのか。そこまで考えて、行動する人は極めて少ない。安藤忠雄は、ひとりの建築家として、仕事などほとんどない無名時代から、そのことに取り組み続けてきたのだ。建築は人間のためにあるのだから。

著書『悪戦苦闘』にその場でサインをして取材陣全員に渡す。気配りの人である。とあるスタッフには似顔絵まで描いてくれた。
だからこそ、安藤は闘い続けなければならなかったのだし、今も闘い続けている。
社会が安藤という破格の存在を受け入れられるか否かは、社会の器の大きさで決まる。社会の器が小さければ、安藤はそれを突破していくしかない。安藤の仕事が世界中に広がっていったのは、当然の成り行きでもあった。
アメリカ、メキシコ、フランス、ドイツ、イタリア、アブダビ、バーレーン、中国、韓国、台湾……。2009年時点で、安藤が取りかかっている仕事の現場の大半は外国にある。外国だからといって、安藤の仕事がスムーズにいくというわけではないだろう。
建設や社会の仕組みの違う海外では、むしろ日本よりもはるかに仕事が難しいはずだ。また、人間の「生」の輝きを失わせる、硬直した社会のシステムがあるのは日本だけではない。これからも、世界中のいたる所で、安藤は既成の枠組みを突破するために、時に怒声をあげながら突き進んでいくことだろう。
闘って、闘い抜いて、大勢の人々と対話しながら、安藤はこの地球の表面を変えていこうとしている。
自伝『建築家 安藤忠雄』の最後を、安藤はこう結んでいる。
『私は、人間にとって本当の幸せは、光の下にいることではないと思う。その光を遠く見据えて、それに向かって懸命に走っている。無我夢中の時間の中にこそ、人生の充実があると思う』
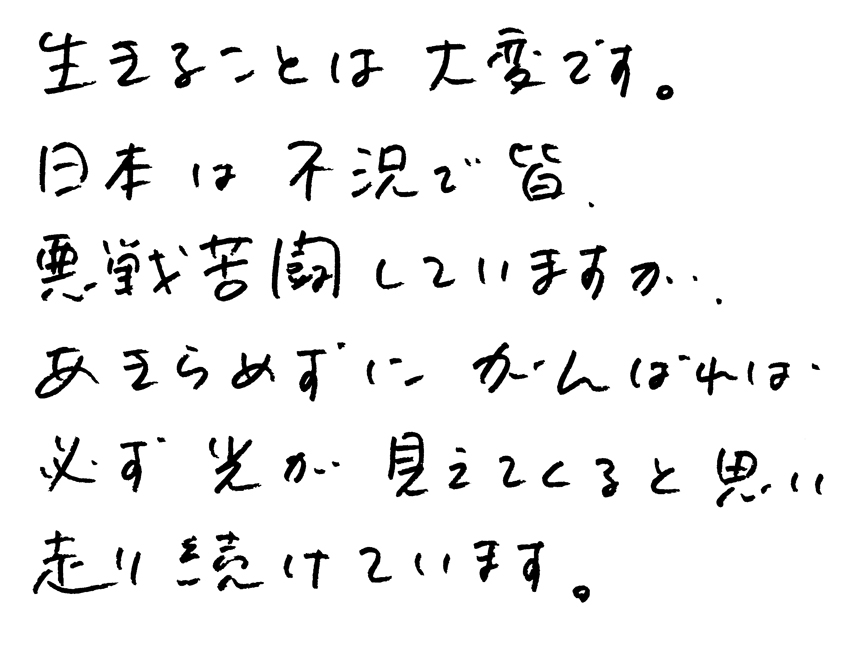
Tadao Ando
1941年大阪府生まれ。独学で建築を学び、’69年に安藤忠雄建築研究所を設立。世界的建築家に。現在、世界中で進行中のプロジェクトは50を超える。プリツカー賞、文化勲章をはじめ受賞歴多数。