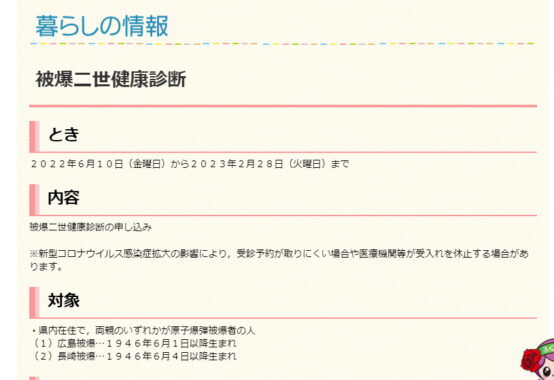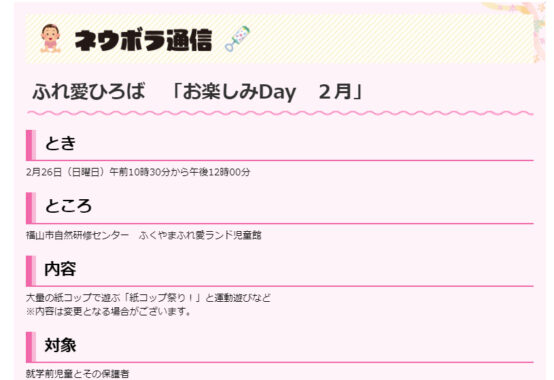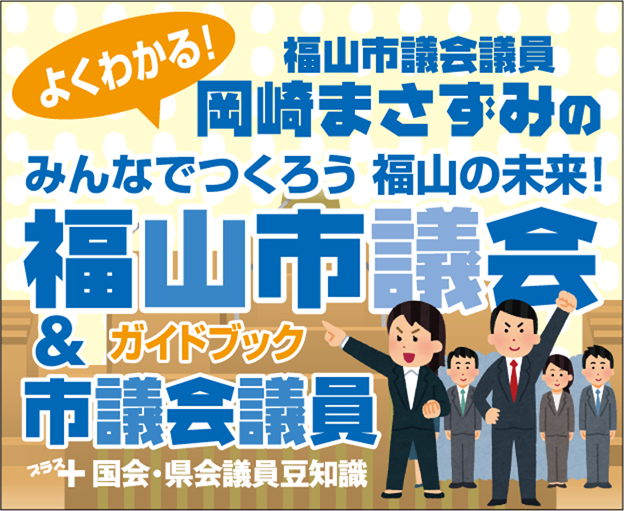【forbesjapan】
2023.05.27
筆者、宮沢賢治の銅像とともに(岩手県盛岡市材木町)
パルバース氏が日本に50年あまり暮らし、自身を「日本人」と感じるようになった経緯には、ある物語があった。
氏は若き日、世界初の人工衛星「スプートニク」打ち上げ成功の衝撃からUCLAでソビエト政治を学び、ハーバード大学ロシア地域研究所へ進んだ後、米国学生協会から奨学金を受けてポーランドに留学。その後、米国へ戻っていったが、ベトナム戦争への批判から再び米国を離れ、「まったくの未知の国だから」という理由で、日本へ。
だが到着したその夜、空港からのタクシーの車窓に揺れる東京の街路を目にした氏は車内で「ぼくは死ぬまでこの国に永住するぞ、ここがぼくの国だ」とつぶやき、その後、「日本人の心をもつようになった」と感じながら日本に滞在し続けるのである。自著『もし、日本という国がなかったら』では、「日本という国は世界にとって、なくてはならない必要な存在」と書く。
また、『ぼくがアメリカ人をやめたワケ』(2020年、集英社インターナショナル刊)では、以下のようにも書く。
「のちにぼくが日本文化に、とりわけ宮沢賢治の作品に深い愛情を覚えたとき、自分の前世は、岩手にある沼の泥の中を泳ぎ回るナマズだったと想像しました。これはたあいのない喩(たと)えに思えるかもしれませんが、自分のことを屈強な兵士、あるいは法衣をまとった宗教の信徒であると考える人と比べたら、そんなに非常識ではないでしょう。自分をナマズと考えることが、この国に溶け込み、なじむためのぼくなりの方法でした。
ぼくは、日本で人生における意味と目的を発見しました。人生で必要なのは、日本文化に対する深い愛情を本、演劇、映画で表現することだということに気づいたのです」
宮沢賢治没後90年の今年、「前世は岩手の沼のナマズ」というパルバース氏に、宮沢賢治の実兄清六氏との親交について、そして、ウェルビーイングや地球環境存続への活動が叫ばれる21世紀の今にこそ賢治を読み直す意味について、以下、ご寄稿いただいた。
私はその家の軒下に立ち、できるかぎり音を立てないように玄関の戸をそろそろと引き開け、おずおずと言った。
「ごめんください」。
1968年8月、宮沢賢治が生まれた岩手県の小さな町、花巻の富沢町でのことである。
正確にいえばそこは賢治の生家そのものではなかった。1945年8月10日、終戦のわずか5日前、花巻は空襲を受けた。まさに「復讐の恐怖」としか言いようのない行為である。幸い、宮沢清六は兄賢治の原稿を家から持ち出し、安全な場所に避難させた。
60代半ばの男性が通用門までやってきた。「はい」と彼は言って、不恰好なこの24歳のアメリカ人を、興味深い目で見やった。